「体調不良で仕事を休んでいるけど、給料が出ない…」「長く休職していて、今後の生活が心配」
そんなときに頼れるのが傷病手当金という制度です。
ただし、申請の際には書類の準備や医療機関への証明依頼など、いくつかの手順を踏む必要があります。
この記事では、現場経験のある医療ソーシャルワーカーの立場から、申請書作成のポイント・医師への依頼方法・準備のコツまでをわかりやすく解説します。
傷病手当金とは|基本のルールと対象者
「体調を崩して働けない…」「長期休養中で給料が出ない…」
そんなときに生活を支えてくれるのが「傷病手当金」です。
傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがにより働けず、報酬が受け取れない期間に支給される生活支援の制度です。
支給条件は次の4つ
- 健康保険の被保険者であること(国民健康保険は対象外)
- 病気やケガで労務不能の状態にあること
- 連続して3日間以上仕事を休み、4日目以降も労務不能が続いていること
- 休業中に給与等を受けていないこと
支給される期間:最大で1年6カ月が限度です。これは初回の支給開始日から数えます。
支給額の目安|どれくらいもらえる?
支給額は、過去12カ月の平均報酬日額の3分の2が基本です。
📌たとえば…
月収30万円の人の場合 → 30万円 ÷ 30日 × 2/3 ≈ 約6,600円/日
※厳密には加入している保険者(協会けんぽや健保組合)等によって微調整があります。
傷病手当金の申請方法|何が必要?
申請先は、ご自身が加入している健康保険の保険者です。多くの場合は、勤務先の総務課などを経由して手続きを行います。
必要な書類と記入方法:
傷病手当金申請書の構成例
- 被保険者記入欄(申請者本人が記入)
- 事業主記入欄(会社側が証明)
- 医師の意見欄(主治医が証明)
- 添付書類(場合により)
医師の証明を依頼する際のポイント
申請書の中でも特に重要なのが、「医師の意見欄」です。ここには、以下のような情報が記載されます。
- 診断名、治療内容
- 通院・入院期間
- 労務不能の期間(働けなかった期間)
💬ここが大事!
医師による証明は「作成日まで」の期間しか記載できません。未来の証明は不可です。
医療機関への依頼方法
- 申請書を持参して受付で依頼します
- 通常、作成には1〜2週間前後かかることが多いです
証明書作成料は保険適用(100点)。自己負担は次の通り:
| 保険負担割合 | 自己負担額(概算) |
|---|---|
| 3割負担 | 約300円 |
| 2割負担 | 約200円 |
| 1割負担 | 約100円 |
※通常の診断書よりも格安です。
作成前にチェック!スムーズに進めるための事前準備リスト
よくある質問|申請時に気をつけたいこと
Q:申請はいつまでにすれば良い?
🟢支給対象期間が過ぎてから2年以内であれば申請できますが、その都度早めに提出した方が支給も早まります。
Q:申請書はどこで手に入れる?
🟢勤務先経由、もしくは保険者の公式サイトからダウンロードできます(例:協会けんぽHPなど)。
Q:何度も提出が必要?
🟢支給は月ごとが基本。1カ月単位で「その月の分の申請書」を作成し、毎月提出する形が一般的です。
まとめ|医師への依頼は早めに!スムーズな申請を目指そう
傷病手当金の申請には、「書類の準備」+「医師の証明」+「会社との連携」が必要です。
医療機関への証明依頼には時間がかかることも多いため、準備は早め早めが鉄則。
証明作成も保険適用なので費用の心配も少なく、気軽に相談してOKです。
📌この記事のポイント
- 傷病手当金は健康保険加入者の生活を支える制度
- 申請書には本人・会社・医師の3者の記入が必要
- 医師の証明には日数がかかるため早めに動く
- 費用は保険適用のため安価で安心


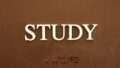

コメント