はじめに|医療ソーシャルワーカーとして働きたいあなたへ
医療ソーシャルワーカーを目指す方の中には、「未経験だけど大丈夫?」「まず何を勉強すればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
私自身、医療現場でソーシャルワーカーとして15年以上勤務してきましたが、仕事をしていく中で「これは勉強しておいてよかった」と心から思える資格がいくつかあります。
この記事では、未経験から医療ソーシャルワーカーを目指す人が、どんな資格を取得すればよいかを、自身の体験や同僚にインタビューした内容も交えて紹介します。
✅ この記事はこんな人におすすめ!
・医療ソーシャルワーカーを目指している
・未経験からのキャリアスタートに不安がある
・何から勉強していいか分からない
社会福祉士:採用条件として必須の医療機関も多数
社会福祉士は、医療ソーシャルワーカーを目指すなら最優先で取得すべき国家資格です。実際に私が勤務してきた病院でも、相談員の採用要件として「社会福祉士の資格保有」が条件になっていることがほとんどでした。
【ポイント】学べる内容と役立つ場面
- 社会保障制度や生活保護、障害福祉制度など、幅広い社会福祉の知識が身につく
- 面接技法や相談援助技術など、実務に直結するスキルが習得できる
- 資格があることで、相談員としての信頼性・専門性を客観的に証明できる
📌 実体験メモ
実際に資格取得後、患者さんやご家族から「資格を持っているなら安心」と言われたことがあります。信頼感は日々の対応だけでなく、資格によっても支えられていると実感します。
精神保健福祉士:これからの時代に求められる専門性
うつ病、認知症など、精神疾患やメンタルヘルスに関する支援のニーズが年々高まっています。そんな背景もあり、精神保健福祉士の資格があると、現場で強みになります。
【ポイント】こんな場面で活かせる
- 認知症の患者さんへの対応やご家族への説明時
- うつ病や統合失調症など精神障害の既往歴がある方の支援
- 精神科病院、地域包括支援センターなど幅広い職場で活躍可能
💡 現場経験者の声
骨折の入院で来られた高齢患者さんに、認知症の症状がありました。本人の不安定な言動や家族対応に苦慮したとき、精神保健福祉士の知識が非常に役立ちました。
福祉住環境コーディネーター:退院支援で力を発揮
退院後の在宅生活を支えるには、住まいの環境整備と福祉用具の選定が不可欠です。医療ソーシャルワーカーとして、ケアマネジャーや福祉用具業者と連携する場面は多く、その際にこの資格が活きます。
【ポイント】実務でのメリット
- 住宅改修や福祉用具の選定に関する基礎知識が身につく
- 専門業者との打ち合わせがスムーズになる
- ご家族やケアマネとの信頼関係づくりにも効果あり
🛠 実務での体験談
退院前カンファレンスで、福祉用具業者さんと住宅環境の調整をする場面がありました。基本的な用語や制度を知っているだけで、スムーズに打ち合わせが進行しました。
ファイナンシャルプランナー(FP):経済面の支援で活躍
意外と知られていませんが、医療ソーシャルワーカーの相談業務には“お金の悩み”がつきものです。
- 「年金だけで生活が苦しい」
- 「施設に入りたいが費用が払えない」
- 「働けなくなって収入がない」など…
FP資格を取ったことで、経済的な困窮に対する支援の幅が広がりました。
【ポイント】FPが活かせる場面
- 公的制度と民間保険・年金制度とのすみ分けが理解できる
- 相談者に適切な機関を案内できる(社会福祉協議会、年金事務所など)
- 実生活にも役立つ知識として一石二鳥
💬 経験メモ
FPの知識で「収入と支出の見通し」についてご家族に説明した際、非常に納得感を持ってもらえました。今では「持っててよかった資格No.1」です。
まとめ|まず一歩を踏み出そう
これから医療ソーシャルワーカーを目指す皆さんに伝えたいのは、「完璧を目指すより、まず一歩を踏み出すこと」です。
紹介した資格はすぐに全て取得しなくても構いません。自分のペースで学びながら、現場での実践を積み重ねていけば、きっと信頼される支援者になれますよ。
✨ 今日が一番若い日。思い立ったら今こそスタートの時です!

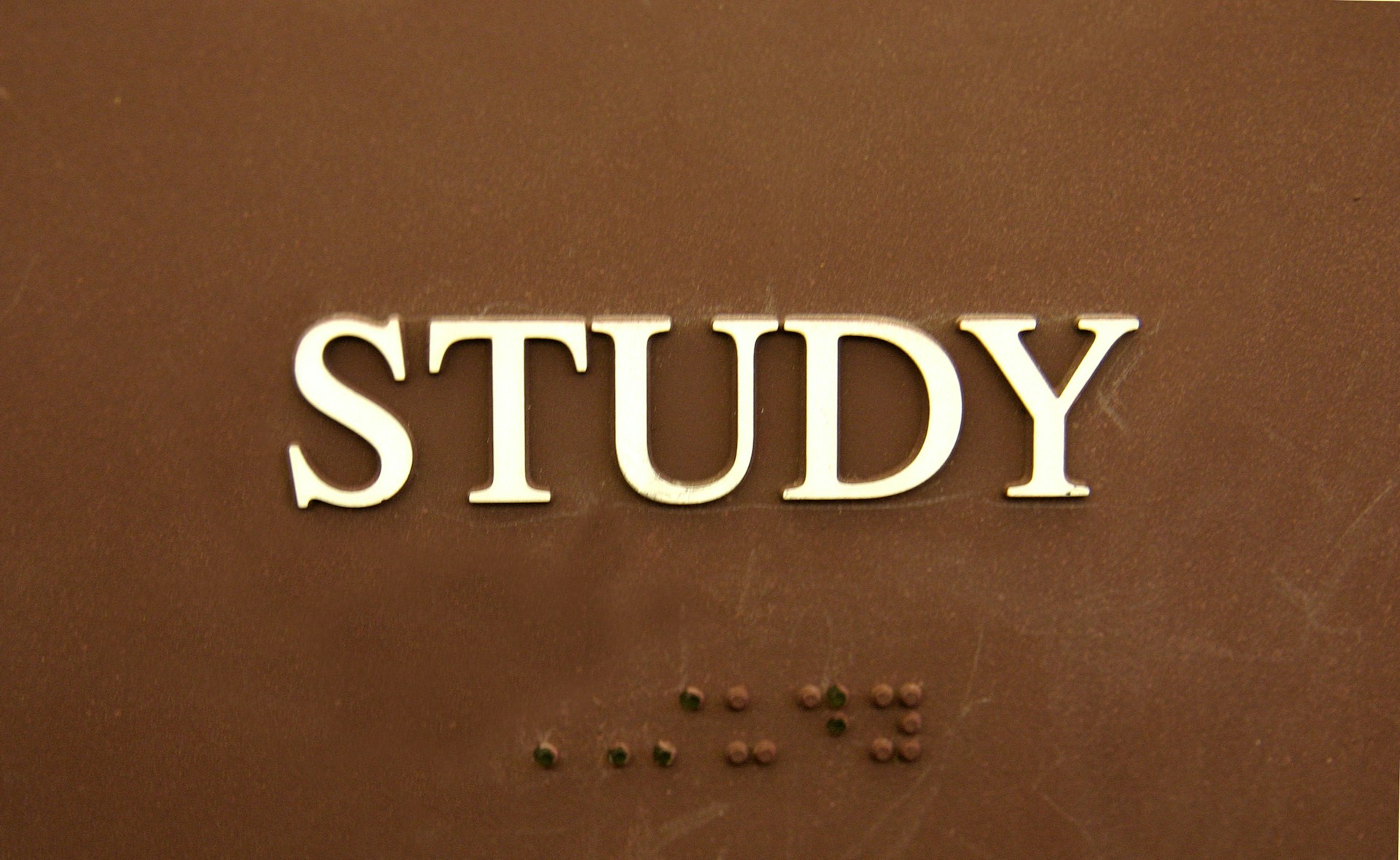




コメント