入院の医療費については公的保険による「高額療養費制度」の減額対象となりますが、食費負担や差額ベッド代、その他自費部分については減額対象外です。
自費部分の支払いが「自分の預貯金だけだと心許ない」と不安に感じる人もいるかと思います。
そんな時に活用したいのが、民間の医療保険からもらえる給付金です。
皆さんも病気やケガで入院したときに備えて、何かしらの保険に加入されているのではないでしょうか。
それぞれの契約内容によって、受け取れる条件や給付金の種類は変わりますので、ご自身の契約内容を見直しておきましょう。
ここでは、多くの方が利用されている入院保障・「入院給付金」の受け取り方や手順をまとめていきます。
入院におけるメジャーな給付金は2つ
入院日数に応じた金額をもらえる「入院給付金」
入院していた日数に応じた金額が入院給付金としてもらえます。
ただし、保障される入院日数には限度があり、それぞれ「支払い限度日数」が定められています。
例)「1回の入院に対して60日分まで給付」など
手術内容に応じた金額をもらえる「手術給付金」
手術の内容に応じた金額が手術給付金としてもらえます。
対象の手術であれば、「一律の給付金が受けられるタイプ」や「手術の種類によって金額が異なるタイプ」があります。
一部、手術給付金の対象外となる手術もあるので注意しましょう。
その他にも様々な給付金が用意されている
入院していなくても給付対象となる「通院給付金」や特定の疾病に対する特約「がん、ケガの特約」など、保障内容は多岐に渡ります。
自分が加入している保険の契約内容をもう一度見直してみると、新たな発見があるかもしれません。
入院給付金を請求する一般的な流れ
ここでは給付金申請の中で、一番申請数が多い「入院給付金」の請求方法についてみていきましょう。
- 生命保険会社へ連絡する
- 生命保険会社指定の必要書類を揃えて提出する。
- 生命保険会社にて支給可否の判定を行う。
- 給付金が指定口座へ振り込まれる。
入院給付金を請求するためには「入院証明書」が必要
給付金を受け取るためには、入院していたことを証明する「入院証明書」が必要となります。
各生命保険会社では「入院証明書兼診断書」「入院・手術証明書(診断書)」という名称で呼ばれていることが多いです。
「入院日数が短い」「給付が一定額以下」「手術を受けていない」等の条件を満たす場合は「病院発行の領収書」等で代用できる場合もあります。
ただし、入院証明書の提出が不要となる条件については、保険会社により異なりますので、
加入している保険会社へ必ず確認してください。
医療機関(病院)から入院証明書をもらうには
申し込み方法と申し込む時期
入院証明書の作成は医療機関の窓口へ申し込みが必要です。
保険会社指定の様式をお持ちの場合は、作成申し込み時に医療機関窓口へ渡しましょう。
保険会社指定の様式が無い場合は、入院証明書に何を記載してもらえば良いのか、事前に確認しておくことをオススメします。
医療機関側も何を書けば良いのか分からないと、作成に困ってしまいますからね。
「入院となった原因の病名」「入院日・退院日」「手術名・手術日」など記載することが一般的です。
作成依頼を掛けるタイミングとしては、退院後または退院日が決まってからが一般的です。
ただし、入院途中でも入院証明書を作成することは可能ですので、下記のような事例では前倒しで作成依頼をすることもあります。
例)入院給付金の支払い限度日数が60日で、現在60日以上入院を続けている場合
どれだけ入院を継続していても60日以上は給付が受けられないので、
入院から60日が経過した段階で入院証明書を作成してもらうのもアリ。
作成にかかる費用と完成までにかかる時間
入院証明書の作成代には費用がかかります。
作成にかかる費用は各医療機関ごとに設定されています。
記載内容に応じて数千円程度の場合が多いです。
記載内容や医師のスケジュール、申し込みの混雑具合いにもよりますが、完成までに1〜3週間程度時間を要します。
余裕を持って申し込みしておきましょう。
あらかじめ入院が決まっている場合は、事前に保険会社から申請用紙を取り寄せておこう
入院予定が決まっている場合は、事前に保険会社へ連絡をして申請に必要な書類を取り寄せておきましょう。
保険会社のホームページからダウンロードできる場合もありますので、ホームページもチェックしておくことをオススメします。
スムーズに入院給付金が受け取れるように、必要な準備は整えておきましょう。

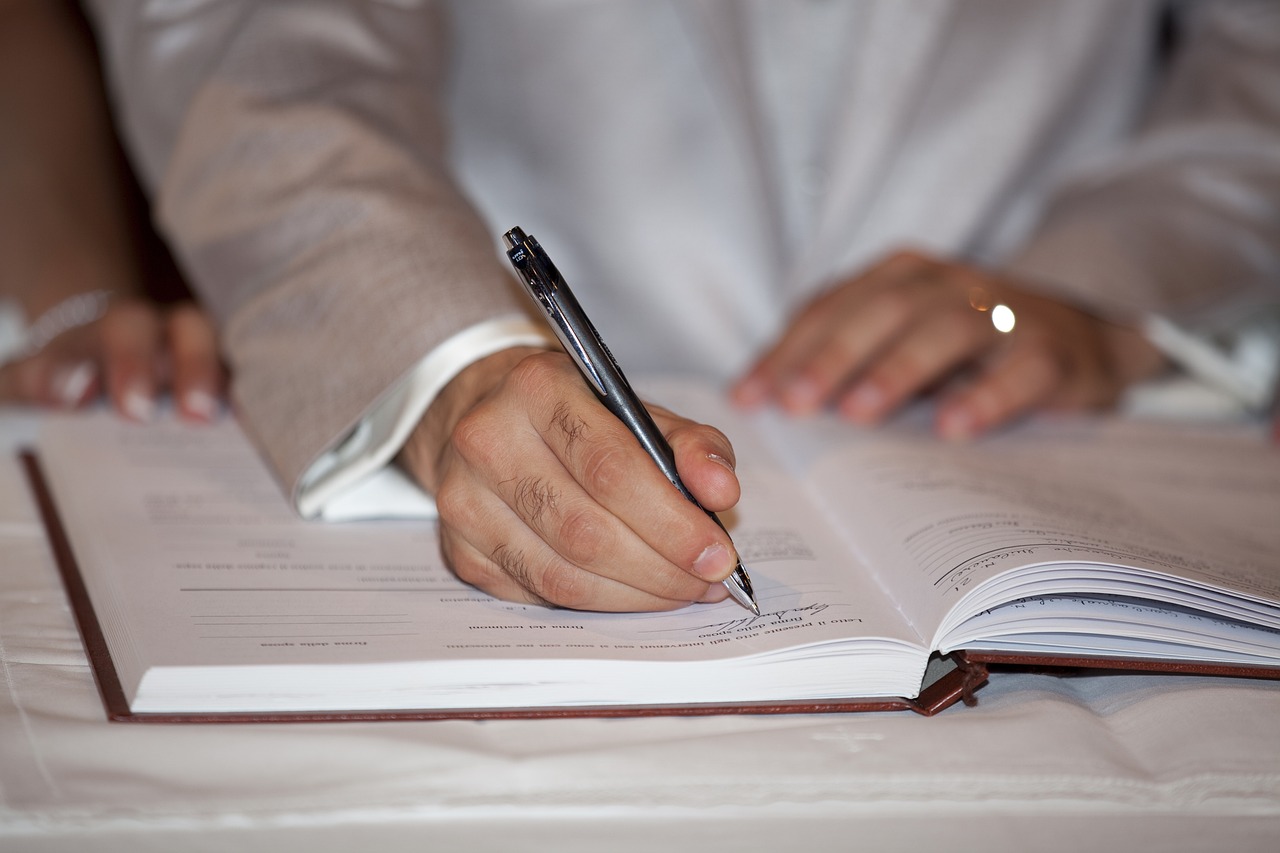



コメント